筑後地域で事業を営む中小零細企業経営者の皆さん、人手不足、経営不振、事業継承といった課題に直面していませんか。もしくは創業や独立を果たしたものの、日々の業務に追われ、新たな学びの機会を逸していると感じていませんか?
私は先日、福岡県中小企業家同友会県南地区センターで開催された「経営AI支援勉強会」に参加してきました 。そこは、久留米・筑後地域をはじめとする熱心な福岡県内の中小零細企業経営者が集まり、AIを経営にどう活かすかを学ぶ場でした。商工会議所や各種経営塾とは少し異なる、実践的な内容が展開されていました。本稿では、その参加レポートをお届けします。
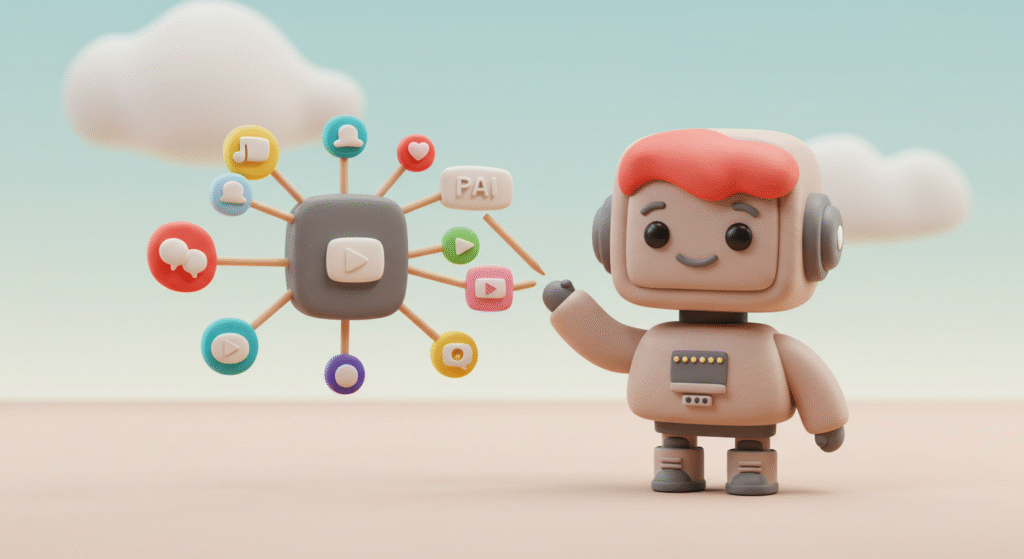
■ 第4回のテーマ:簡易専用AI「NotebookLM」の使い方
今回の経営AI支援勉強会で中心的なテーマとなったのが、GoogleのAIツール「NotebookLM」です。
一般的なChatGPTなどがインターネット上の膨大な情報から回答を生成するのに対し、NotebookLMはユーザーがアップロードした自社の資料(社内規定、顧客データ、過去の議事録など)のみを情報源として回答を生成します 。これにより、AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」がほとんど発生しないという特徴を持っているそうです 。
つまり、自社の情報だけで学習した「自社専用のAI」を構築できるツール、と理解してよろしいと。
■ AIは経営課題をどう解決するのか?具体的な活用事例
経営AI支援勉強会第4回では、講師であるりょうちく支部の柿元千德氏から、NotebookLMの具体的な活用事例がいくつか紹介されました 。
経営の現場で散見される課題に対し、AIがどう貢献できるか、その可能性が見えてきます。
事例1:社内マニュアルと規定をAI化 → 人手不足と教育コストに対応
多くの企業が人手不足に悩む中、総務や経理部門への問い合わせ対応や新人教育は大きな負担となっています。
NotebookLMに就業規則や各種規定、業務マニュアルなどを登録しておくことで、従業員からの質問にAIが自動で回答する仕組みが簡単に構築できます 。例えば、「この経費はどの書式で処理すればよいか」といった質問に対し、社内規定に基づいた正確な答えをAIが即座に提示します。これにより、総務担当者の負担や時間が軽減され、新入社員も自律的に問題を解決できるようになります 。これは社員教育や資格試験の教材作成にも応用可能だそうです 。
今回柿元さんは、技能実習生や高度人財の外国人雇用を実施している企業さん向けの、画期的な社内情報共有の仕方も教えてくれました。
事例2:顧客データをAIで分析 → 営業戦略の立案と事業継承
営業活動は属人化しがちですが、AIを使えばその知見を組織の資産として蓄積できます。
過去の顧客とのやり取りや新規顧客のプロファイル情報をNotebookLMに読み込ませ、自社の営業方針と照らし合わせることで、AIが個別の顧客に合わせた具体的な営業戦略(ネクストアクション)を提案することが可能になります 。
ある失注案件について、顧客情報と自社の営業マニュアルをAIに読み込ませたところ、「顧客層との年齢ギャップが戸惑いを生んだ可能性」を失敗原因として分析し、「年代の近い営業担当者との面談機会を設ける」といった具体的な次の一手をNotebookLMが提示した事例が紹介されました 。これは経営不振に悩む企業の営業力強化に直結するだけでなく、ベテランから若手へのスムーズな事業継承のツールとしても機能しそうです。
事例3:書籍や動画をAIで要約 → 経営者の学習効率を最大化
創業期や独立直後の経営者は、時間が何よりも貴重です。NotebookLMは、書籍一冊を丸ごと読み込ませてマインドマップ形式で整理したり 、長時間のYouTube動画を要約させたりすることができます 。これにより、インプットの時間を大幅に短縮し、効率的な自己学習が可能になります。移動中の車内で音声学習することも可能です 。NotebookLMは、まさに現代の多忙な経営者のための生成AIツールと言えるでしょう。
■ NotebookLMの導入と費用
これだけの機能を持つツールですが、導入のハードルは決して高くない様です。
- 無料版: データ50個まで登録可能です 。
- 有料版: Google Workspace(月額1,600円程度/1人)の契約に含まれており 、登録データ数が300個に増え、セキュリティも強化されます 。
まずは無料版から試用し、その効果を実感した上で有料版へ移行するのが現実的な選択肢だそうです。
講師の柿元さんが無理に商品を押し付けたりしてこない処も安心できました。
■ まとめ:AI活用は、もはや選択肢ではなく必須の時代へ
今回の第4回テーマで取り上げていたNotebookLMは、自社の資産である「情報」を最大限に活用し、組織の意思決定を支援する実践的なツールであることを示すものでした。

皆さん、お疲れ様でした❣